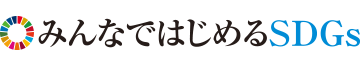Vol.01 目標から当たり前の行動に、SDGsが実現する未来
中日新聞「みんなではじめるSDGs」では
各分野でSDGsを実践される方たちにリレーインタビューを行います。
今回は国連地域開発センター所長村田重雄氏に
SDGsの現在地や展望についてお話を伺いました。

国際連合地域開発センター(UNCRD) 所長
村田 重雄氏
進捗は一進一退
ー社会情勢不安が続く中、SDGsの進捗にはどれくらいの影響があったのでしょうか。
村田 特に大きな影響を与えたのはコロナ禍です。健康面(ゴール3)では、約10年分の平均寿命の延びが帳消しになりました。貧困(ゴール1)も、減少傾向だったものが2019年から再び増加し、2022年にようやく元の水準に戻りました。戦争や紛争も大きな影響を与えています。平和と公正(ゴール16)については、2021年から22年にかけて民間人の死傷者数が39%増加。23年にはさらに72%増加するなど大きく後退しています。
ー日本の状況はいかがでしょうか。
村田 日本は、文化的背景からジェンダー平等(ゴール5)の進展が厳しい一方、インフラ産業(ゴール9)は高い水準を維持しています。2015年からの伸びで見ると、再生可能エネルギー(ゴール7)の伸びが顕著で、パートナーシップ(ゴール17)も毎年改善しています。特に中部圏では、企業や学校の意識が高いと感じています。

先日開通した東海環状自動車道本巣IC
当たり前の考え方に
ー意識をしっかりともち、持続していくことが大切ですね。一過性で終わらせないために何が必要でしょうか。
村田 スタートアップ企業からお話を伺うと、SDGsははもはやブームではなく、基盤にある考え方、普遍的な価値観になってきています。2030年という目標年はありますが、その後もSDGsの取り組みは続いていくものだと思います。現在、国連本部でも2030年以降の方向性が検討されています。
ー若い世代のSDGsへの意識はどうですか。
村田 現在の学生たちはSDGsという概念を持つことで具体的な取り組みができています。特に今の小学生にとってはSDGsが当たり前の環境です。彼らが成長すれば、達成度の低い目標も進展するでしょう。自分たちの地域と結びつけて考えることで、さらに関心を高められるはずです。