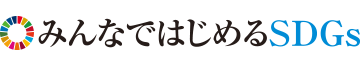Vol.03 明治の記憶を未来へ。次の時代へ繋げるバトン
中日新聞「みんなではじめるSDGs」では
各分野でSDGsを実践される方たちにリレーインタビューを行います。
今回は博物館 明治村 学芸員 中野裕子氏に
文化継承の取り組みについてお話を伺いました。
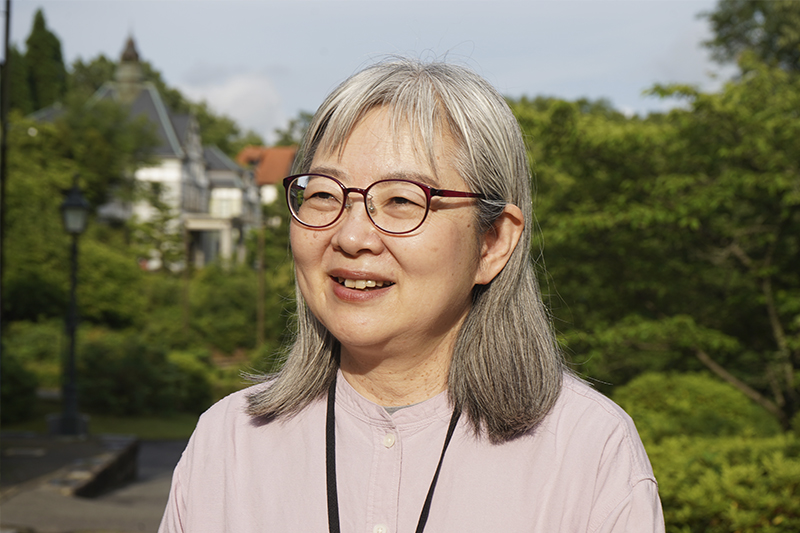
博物館 明治村 学芸員
中野 裕子氏
技術や文化を発展に
ー博物館 明治村の役割を教えてください。
中野 明治という時代を後世に伝えることを役割とし、64件の建造物、3万点以上の歴史資料を保存・展示しています。昭和15年、鹿鳴館が取り壊されたのをきっかけに、初代館長の谷口吉郎が後世に残すべき文化を守りたいと思ったことから博物館 明治村の構想は始まりました。
ーおすすめの見方、歩き方はありますか。
中野 建物ひとつひとつにストーリーがありますので、それを辿っていくと面白いと思います。移民関連の建物群はハワイ、シアトル、ブラジルの建築が集められており、日本人移民の歴史の流れを物語っています。阪神淡路大震災で被災した芝川又右衛門邸には、煙突が折れ暖炉の跡から外が見えたという体験の記録も残されています。堀川の近くにあったという東松家住宅は元は油屋でした。増築を繰り返した内部構造も興味深いですし、名古屋の文化が色濃く残されています。こうした記録は、「自分たちの町ってどうやってできたんだろう」と振り返るきっかけにもしてもらえると思います。

堀川貯蓄銀行を営んでいた東松家住宅は
切妻造りの屋根をのせた珍しい木造3階建て
過去に学び未来を想像
ー明治村から学ぶことができるSDGsについて教えてください。
中野 明治時代の人たちも、今で言うSDGsのような発想で欧米の進んだ技術や文化を学び、自国の発展に活かそうとしてきました。これは現在の「持続可能な社会づくり」にも通じる考え方だと思います。建造物を移築して新たな場所で活用するサーキュラーエコノミー(循環経済)的な考え方や、歴史的建造物に新たな価値を見出す「まちづくり」の視点も養えるのではないでしょうか。
ー今後の展望はいかがでしょうか。
中野 「誰一人取り残さない」社会を実現するためには、過去から学び、現在を理解し、未来を創造する力が必要です。「残し」「伝えていく」ことも簡単ではありません。明治村はその架け橋とになっていきたいと考えています。

2階には茶室が設けられ、外光による照明や
おもてなしの工夫が細部にちりばめられている

震災の記録も伝える芝川又右衛門邸